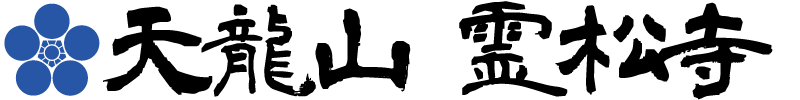法話1.言葉について
日本人の話し言葉のスピードは1分間に300字〜350字程度が聴きやすいといわれます。
そうすると3分間に話せる文字数は900字〜1050字ほどという計算になる。
また、人間が何かに集中していることができる時間は大人で50分程度、15分ほどの周期でピークが来るそうです。マックスは90分程度と聞いたことがある。学校の授業はこの集中力のデータ?を参照しているのかもしれません。そうなると、最も集中できる15分間には大体5000字程度の話し言葉を集中して聴くことができるということになります。しかし、話し言葉では「あ〜」とか「え〜」とか、つなぎ言葉(フィラーワード)も多用されるので、書き言葉の方が無駄がないと言えるでしょう。でも、このような「間投詞」「冗長語」は「間」を繋ぐ効果などがあり、単に無駄で耳障りなものとも言えないわけです。
さて、「法話」は時と場所によって臨機応変りんきおうへんに話す時間が決められるわけですが、かつて山田無文やまだむもん老師ろうしなどは「三分間法話」(1982年初版刊行本)をされていました。何故3分間になったのか、だれが発案者なのか知りませんが、最近まで多くの宗派の僧侶たちがこれを踏襲していますね。
ところで、禅仏教などでは、言葉というものは道を示す「道しるべ」であると言われることがあります。修行を進めるためには必要不可欠なものですが、どうも第二義的なものと軽んじられる傾向がある。しかし、この道しるべは「悟り」への道標です。悟りという言葉は特定の心境・境地を指すようですが、あいまいなところがあります。自分がそこに到達しているかが分かりにくいところがあって、道元禅師どうげんぜんじなども如浄禅師にょじょうぜんじ(お師匠さま)に向かって「安易に自分の境地を認証しないでください」と言っています。それで別表現を考えて、例えば「自己身心の理想的状態」「泰然自若たいぜんじじゃくとした境地」などという表現を思案してもなかなかうまく言えません。それで「筆舌ひつぜつに尽つくしえぬ絶言絶慮ぜつごんぜつりょのところ」と否定的表現になるわけです。そうなのですが、私たちは毎日言葉の中に生きており、それによって自己の意思を決定したり行動したりしているわけで、もっというと、私たちの心は多くの部分を言葉によって作られているとも言えます。ですから私たちは、言葉というものには絶大な力があることを知っております。我々の日常や人生は言葉に縛しばられているとも言えますね。それを「呪縛じゅばく」と考えるか「道標どうひょう」と捉えるかです。
法話2.活きた言葉
小林秀雄の『無常ということ』という文に「生きている人間などというものは、どうも仕方のない代物だな。何を考えているのやら、何を言い出すのやら、仕出来すのやら、自分の事にせよ他人事にせよ、解った例があったのか。鑑賞にも観察にも堪えない。其処に行くと死んでしまった人間というのは大したものだ。何故、ああはっきりとしっかりとして来るんだろう。まさに人間の形をしているよ。してみると、生きている人間とは、人間になりつつある一種の動物かな」というのがありました。中学か高校の授業で聞いて、その時は活きている人のほうが存在感がしっかりと感じられて、死んだ人はその記憶も時間とともに曖昧に薄れてゆくのだから、小林のこの言葉は納得いかないなあと思っておりました。
しかし最近、小林の考えにも一理あると思えることがあります。というのも、生きている人間というものは絶えず意見を変えたり優柔不断であったり変わるものだから、随分いい加減な感じだけれでも、まあそれもよく考えれば絶えず進化発展(?)していると言えないわけでもないのです。一方死んだ人の情報というのはいったん打ち止めになっているわけですし、例外もありますが、人格的評価というものもある程度確定しているのですから、しっかりした印象です。ですから、小林の見解にも頷けるのですが、ここでは生きた人間もまんざら情けないだけではなく、死んだ人よりいい面があるということが言いたいわけです。
「対機説法(たいきせっぽう)」という言葉がありまして、これは仏教においてお釈迦様が相手に即した縦横無尽のお説法をされたことをいうのです。こういうことは、死んだ人間にはできません。もっとも立派な人間の言葉というのは、その人物が死してなお、人々に感化を与えるということもあります。これはむしろ、聞き手(受信者)の心の在り方の問題です。普通はやはり生きた人間が活きた会話の中で、おたがいに影響を及ぼしあうような言葉のやり取りをおこなうわけです。こう考えてみますと、生きた人間は危なっかしい部分もありますが、まんざらでもないと思うわけでして、そういう他者に感化を与えるような言葉をかけられるような人になりたいものです。
そのためには、自分がぶれていてはなりません。まっすぐに立って如何なる状況においても的確な判断と柔軟な発想ができるのでなければなりません。そうなるためには、日頃から坐禅で心胆を鍛えておかなければならないと言いたいのです。とてつもなく難しいけどね。
法話3.西行と桜と釈尊
「ねがわくは、はなのもと(した)にてわれしなむ、このきさらぎのもちづきのころ」とは西行の歌である。
日本人にとっての「はな」は平安末期頃からは「桜」いうことになってくるようである。
この歌の後半の「如月(きさらぎ)」とは二月のことであり、「望月(もちづき)」とは十五夜の満月をいうのであるから、これは二月十五日を指しております。
ということは、それは釈尊の涅槃入滅の日ですから、釈尊の死が西行に明確に意識されていたことは間違いないでしょう。
桜は日本人にとって「魂の依る樹」であり、精神の帰趨する場所のひとつですが、その下で満月を見上げながら、釈尊と共に死ぬというアイデアは、いかにも西行らしいロマンティックな設定(しつらえ)ではなかろうか。それにしても、桜にもたくさんの種類があります。今は「ソメイヨシノ」がよく知られていますが、これは比較的に新しい日本産の栽培品種です。西行の見た桜、思い描いた桜は違うと思います。最近YouTubeを見ておりますと、最も長命な桜の部類は「山桜」や「枝垂れ桜」、「エドヒガン」の類ということでした。長寿の見事な桜の下に立ってそれを見上げれば、誰もが「ああ、もういいや」という気持ちになるように思えます。
桜を歌ったものといえば、他に「散る桜、残る桜も、散る桜」という良寛の歌もありますね。私たちの寿命はやがて尽きて死が訪れます。例外はありません。これは、桜の花の散る姿を見て生死無常を感じつつ、そこに自らの行く末(死)を重ねた良寛の歌だと思います。爛漫と咲き誇る桜花の様子は生命力に満ちています。しかし、花の季節は永遠に続くものではありません。その儚さを受け入れる時はじめて、生命の尊さと重なり合った本当の桜の美しさがわかるような気がするのです。
法話4.「ご縁を愉しむ」ということ
「一期一会」という言葉は、今を大切にしよう、人との出会いを大切にしようという「生きることへの真剣さ」を思い出させるところがあります。それは確かに良い教訓ですが、余りに必死過ぎて、少し窮屈な気持ちを持つのは私だけでしょうか。最近はもうちょっと肩の力を抜いて「ご縁を愉しむ」といった言い方のほうがしっくりくるように感じます。
物事はすべてが計画的に運ぶことも、論理的に理解されることもありません。隠れた論理によって支配されているかもしれませんが、私にはわかりませんし、だからと言って強い意志の力でコントロールしようとしても、それだけですべてを解決できるわけでもない。
「縁」というのも隠れた理(ことわり)なのではないかといわれるかもしれませんが、むしろ、そうした物事に隠蔽された何かを追究するのではなく、ありのままに受け入れて、そのこと自体を愉しむという姿勢が良いと思えてきています。それが自分にとって良いことであろうと都合の悪いことであろうと「生きることの隠された意味」(エルケ・ハイデンライヒの本『エーリカあるいは生きることの隠された意味』のタイトルの一部)として、それを愉しむことが本当に真剣に生きることになるのではないかと思い始めています。
法話5.柳緑花紅
禅で好まれる言葉です。道元禅師も一休禅師も沢庵和尚もこの語を珍重しました。典拠は蘇軾(そしょく)の「柳緑花紅、真面目」といわれています。
毎歳訪れる季節のありのままが「真実相」だというのであれば、五月は青葉の時節です。葉桜をはじめとして若葉の萌え出る新緑の季節であり、新茶畑の眩(まばゆ)い景色が印象的な季節ですね。柳はというと、晩春の季語として「青柳」の語が使われるから、この言葉の前半は、実にこの季節の風物を代表していると思います。(西洋磁器にウィロー・パターン、ブルー・ウィローといった図柄がありますね。ミントン創始者のトマス・ミントンが東洋陶器の図案を模して始めました。そこにはチャンとクーン・セの悲恋の話がついてくるのですが、それはともあれ、晩春を思わせますね。)
後半の「紅い花」はいったい何を思えば良いでしょうか。中国的には牡丹(ぼたん)・芍薬(しゃくやく)、椿(つばき)、梅、桃などありますが、桃でしょうか。しかし、春の花はまことに多彩で何も赤に限ったわけでもありません。私見をいえば、淡いピンクの桜花の後に、鮮やかな紅い花といえば、私は「皐(さつき)」を思い起こします。日本原産でツツジの仲間(ツツジ科)ですね。サツキとツツジの見分け方をネットで調べてみますと、いろいろ書いてありましたが、葉の面に艶のあるのがサツキで、細かな毛の生えているのがツツジだというのもありました。「皐月(さつき)」は五月の謂いで、同じ読みの皐はこの月の季語です。そして、この月の季語の中には「時鳥(ほととぎす)」があり、それは花の皐月の別称でもあり、鳥のホトトギスの喉元の紅さは正しく皐の花弁そのものの色合いのように思えてならないのです。そんな想像を膨らませてくれるこの言葉は、実に印象的で刺激的なものです。
最後に書かれている「真面目」とは「しんめんもく」と読みます。真実の姿、ありのままの姿といった意味ですが、個人個人が脳内で想い描くイメージは違っているとしても、「柳は緑で花は紅だ」なんて言葉は、当たり前すぎて気にも止まらず、読んでも普通ならパスしてしまうと思うのですが、そこを「真面目(まじめ)」に再考するように促してくる表現が用意されているのです。つまり、そこに「真面目(しんめんもく)という言葉がアンカー(錨)のように突き刺さっているのが絶妙だと思います。この最後の言葉に促されて、私は「柳は緑花は紅」という表現の意味をより深く読み返してみようと思いました。
法話6.生きがいについて
みんなほめられるとうれしい。ほめられるとやる気がでる。ほめられると幸せな気持ちになる。
歳を重ねて、だんだん褒(ほ)められることが無くなると、生きる意味を見失う。何のために生まれてきたの?何のために生きているの?苦しくても頑張ってきたけれど自分の人生は何だったのかな?
もしも、神さまや仏さまが見ていて下さって、ちゃんと見守っていてくださって、誰に褒められなくても、正しく認めてくださるのだと信じられるなら、人は生きていける。白隠慧鶴の『草取唄』に、こういう唄がある。
神や仏を祈らずとても、直(すぐ)な心が神仏。人が見ぬとていつわるまいぞ、我と天地がいつか知る。鈍(どん)な者でも正直なれば、神や仏になるがすじ。
ともかく、お天堂(てんとう)さまが見ていてくれることを信じることができて、神仏の求める行いをなすことが人に生きがいをもたらすという、このシンプルさが現代人には難しいのでしょう。それゆえ、現代人は何か別の理屈をつけて、生きがいを努力して見つけ出さなくてはなりません。
渡邊次郎先生の『自己を見つめる』という本に「生き甲斐」の一章があります。その中に次のような文章があります。
自分の心のなかの深い奥底から湧(わ)き上がる必然的な促(うなが)しに突き動かされて、その奥深い内面的な要求を充足させようとすることをしないかぎりは、ほんとうの生き甲斐は、けっして成就しないであろう。私たちは、自己自身を断じて欺(あざむ)いてはならない。誠実に、真剣に、自分を見つめ、自分は真実には何を欲しようとしているのか、自分には何ができるのか、自分に許された最も大切な可能性とは何であるのかを、真摯(しんし)に問い直し、自己自身の進むべき道を直視し、熟考しなければならない。
そして、そういう内面的要求は人間の情意(気持ち)を満足させるものでなくてはならない。そうでなければ人間はけっして幸福にならないとも述べられています。生きがいのある人生は、自己の存在の根源との合致(がっち)であり、そうした生きがいある人生の道は、自分の心の奥底から呼ばわる声の中で、ほのかに示唆(しさ)されるというのです。ハイデガー研究者であった先生の脳裏には「良心の呼び声 (Stimme des Gewissens) 」という言葉が想起されていたと思います。そして、どういう形にせよ、また、どういうタイミングにせよ、生きがいを見つけることができた人間は、よい人生だったと満足して最後を迎えることができるのだと思います。どんなにお金を稼(かせ)いでも、どんなに出世しても、どんなに長生きしても、そういう基準によっては人間の幸福度は測れないと思います。
法話7.執著と無執著(こだわりとこだわりなさ)
原坦山(はらたんざん)は明治初期の禅僧です。15歳で昌平坂(しょうへいざか)学問所に入って儒学・医術を学んだが、旃檀林(せんだんりん)(後の駒澤大学)で講義を行った際、大中京璨(だいちゅうきょうさん)との論争をきっかけに20歳(または26歳)のとき、大中京璨の師の英仙に就いて出家。三河国青眼寺、宇治興聖寺で修行を重ね、風外本高(ふうがいほんこう)の下で悟りを開き、大中京璨の法を嗣いだと言われております。心性寺、最乗寺の住職を歴任し、1879年には東京大学印度哲学科の最初の講師となり、東京学士会院の会員、曹洞宗大学林総監となられました(wiki)。この禅師に有名な話があります。大きな川を渡ろうとした二人の修行僧、そのひとりが原坦山で川を渡るのを躊躇(ちゅうちょ)していた女性をためらいもなく担(かつ)ぎ上げて渡してやったところ、後で同僚に女性に触れたことをたしなめられたというのです。その時、彼は「お前はまだ女を抱いておるのか、わしはとっくに川でおろしてきたのに」と笑ったという話。これは「こだわり」「執著」を考える時の逸話によく登場します。
最近では2017年12月に刊行され、2018年4月段階で第5刷を出した『座右の寓話』(戸田智宏)という本にもアレンジされて使われておりました。原坦山の態度は潔く、清々(すがすが)しいですね。
ところで、「拘(こだわ)り」という言葉は、禅・仏教では未熟の代名詞のように扱われます。しかし、拘りが新しい創造に繋がることもある。今の時代はそういう価値観もある時代ではないでしょうか。それに、拘りや執着は生きている証(あかし)であるとも考えられるのです。そもそも科学の研究における偉大な発見や発明などは、弛まぬ努力とこだわりからはじまるのです。
和辻哲郎(わつじてつろう)先生は『沙門道元(しゃもんどうげん)』という著書のなかで、出家と在家の価値観は別物と言っていますが、一考に値すると思います。両者の価値観のどちらが良いとか、悪いとかは簡単に判定できない場合もあります。また、自分がどちらの立ち位置にいるかを反省することはとても大切なことです。しかも両方の立場を理解してかからなければならないので難しい問題です。まあ、先の原禅師に言わせれば、こんなふうに思考することもすでに「要らぬこだわり」なのかも知れません。
法話8.感動は「我見」を忘れさせる
一雨ごとに鮮やかさを増す緑の五月の木々をみていると、杜甫の絶句を思い出します。
江碧鳥愈白 江(こう)碧(みどり)にして鳥いよいよ白く
山青花欲然 山青くして花然(もえ)んと欲す
今春看又過 今春看(み)すみす又過ぐ
何日是帰年 何(いづ)れの日にか是(こ)れ帰年(きねん)ならん
この詩と初対面した時の感動は今も新鮮に思い出されます。瑞々(みずみず)しい自然の情景とやるせない詩人の心情が伝わってきます。まるで自分がそういう風景の中に実際に身を置いて、鬱々(うつうつ)としている詩人の心に寄り添って共鳴しているように感じるのです。
ところで、ひとは優れた芸術作品や美しい妙景に出会うと「我(われ)を忘れる」、「茫然(ぼうぜん)自失」することがあります。時にはこれが言いようも無く心地よい体験となります。
人間はいつもエゴと闘っています。仏教では「我見」を捨てることを求めますが、それは実に困難な道です。不可能といってもよいから、逆にそれが「人間存在の根っこである」と宣言する者もいるのであります。それなのに、美しいものは容易(たやす)く私たちを魅了します。魅了して、夢中にして我を忘れさせます。これ、仏教修行に役立てることはできないのだろうか。残念ながら、こうした忘我(ぼうが)状態は長続きしないのが玉に瑕(きず)なのです。それでもちょっとした気分転換にはなります。一方で、こういう体験をすると、その記憶がどこかに残されて追体験をしたいと思うことがあるかもしれません。これが執着を産むなどと考えると、まるで薬物の依存症を彷彿(ほうふつ)させるのですが、忘我の体験というのは、求める気持ちを忘れずに持ち続けて生きていると、どこかで出会えるものだと思います。私たちが美術館の展覧会や博物館のイベントに出かけたいと思う気持ちの中には、きっとそういう記憶が影響を与えているのかもしれませんね。あまりガツガツせずに自然体でそういう機会の訪れを待ちましょう。
法話9.「葛藤」とはどんな言葉?
ヤマノイモや薮(やぶ)カラシなど、蔓草(つるくさ)が力を増す梅雨時に、「葛藤」について思います。
この言葉を「かっとう」と読めば、「もつれること」「悶着」「あらそい」のイメージです。植物としては「つづらふじ科」のつる草のことを指すようです。つる草はなかなかのくせ者で、すごいスピードで成長して、纏(まと)わり付かれた花木は力を奪われてしまいますから、厄介ものだという、あまり良くない印象を持たれているところがあります。しかし逆に言えば、この植物は生命力がものすごく強くてしたたかなのです。
道元の『正法眼蔵』には「葛藤」と名付けられた一巻があり、「師資の同参究は仏祖の葛藤なり」などと示されております。これらの説示は修行にあたっての師資(師匠と弟子)の濃密な関係を表しており、人と人の長く複雑な相互交流なしには師資相伝の一大事は成就しないことを、誠に的確に示唆しているように思えるのです。
そこには、嫌がられるようなネガティブイメージはありません。むしろ、つる草の持つしたたかな命の息吹が師資の濃密な師弟関係に結びつけられ、そうした活力なくして「師資相承」「仏心の授受」といった大事は、なし得ないのだと云われているのではないでしょうか。
ところで、葛(くず)は「葛粉(くずこ)」の原料で、それは大好きな和菓子の材料ですし、その蔓(つる)は「かずら編み」などの工芸品に使われています。「ツルムラサキ」も、最近注目されているスーパー野菜ですね。さらに、朝顔やクレマチス、ポトス、ハツユキカズラなどのつる草は、ガーデニングには欠かせない観賞用植物としても重宝がられております。こうして見ると、つる草は大変有用な面を持っていて注目株ですから、現代人には好印象もあるようです。
法話10.イソップの寓話
人と森の神サテュロスが仲良しになりました。この神様は半人半獣の姿の神様で、上半身が人間で、下半身は山羊か馬の姿で描かれることが多いです。ギリシャ・ローマ神話に登場します。
寒い冬のある日、人は両手に「フウフウ」と息を吹きかけました。森の神は「一体何をしているの?」と尋ねました。人は「手をあっためているんだ」と答えました。夕食時になりました。熱々のスープ(かゆ?)を手にした人は、また「フウフウ」と息を吹きかけました。「何してるんだい?」とサテュロス。「冷ますためだよ」と人は答えました。森の神さまは急に立ち上がって「ボクは森に帰るよ」と出ていってしまいました。
これはイソップの作と言われている寓話のひとつです。ではなぜ、サテュロスは出ていってしまったのでしょうか?その理由は「同じ口から出る息で、あっためたり冷ましたりする人間なんかと一緒には住めないよ」というのです。この話にはどんな寓意があるのでしょうか。色々考えられますね。心底をわかりあうことができない相手とは友達になれないという教訓かもしれません。
私はこう考えてみました。ここでは人間の吐く息が取り上げられていますが、私がそこから連想したのは、同じ人間の口から発せられる「言葉」です。言葉は人と人の間で交わされます。そして、人々を「幸せな気持ち」にさせるものです。しかし、一方で人の言葉が多くの他者を「不幸」にすることもあるのです。言葉はまさに「両刃の剣」で人を幸福にも不幸にもしますから、何とも恐ろしい人間のツールです。
さらに、ひとつの言葉が他人を傷つけるだけでなく、自分にも大きな痛手を与えることがあります。最近「いじめ」が社会問題になっていますが、その多くの部分が「悪口や嫌がらせの言葉」だそうです。「言葉の暴力」です。それに「二枚舌」などという言葉もあって、言葉を巧みに使って人々を翻弄する不届きものもいますから困ってしまいます。 そういう言葉を使うニンゲンの「不気味で」「そら恐ろしい」ところが、神様に嫌悪感を与えたのかもしれないと思いました。そういうふうに言葉を操る人間は神様からしたら信用ならない輩(やから)なのです。
息も言葉も人間の口から出るものです。そして両方ともとても便利なものです。でも、その使い方が問題です。よい使い方をしないといけません。道元禅師に「学道の人、言を出さんとせん時は、三度顧みて、自利、利他のために利あるべければ是れを言うべし。利、無からん時は止まるべし」〔正法眼蔵随聞記〕という言葉があります。誠に心に留めねばならぬ箴言(しんげん)であると思います。
法話11.「呑却」ということ
「水に流す」という譬(たと)えがあります。何事かを赦(ゆる)すということですね。なかなかの寛容精神です。しかし、寛容でありたいものだと思っていても、自分のこととなるとうまく気持ちを制御することができないこともあります。そういう時には「腹に納める」ことを考えます。つまり、「吞み込む」わけですが、これを禅では「呑却」という。「ドンキャ」とか「ドンキャク」と読むようです。
これができるのは、実に太っ腹な人物であります。布袋(ほてい)和尚のようなイメージ。確かに、ちょっとしたことならできそうですが、なんでも呑み込むというのは難しい。自分の好みもあるし、毒の強いものや喉(のど)を通らないような代物(しろもの)もあります。
私は「世の中に本当に大切なものはそれほど多くはない」と考えて生きてきました。どういうキッカケでそう思うようになったかは覚えていませんが、随分と幼い頃、小学校に上がる前に、そんなことを思いついたようなボンヤリとした記憶があります。そういう考えがあれば、吞み込むのも少しは楽になるように思います。しかし、「腹ふくるる想い」となって消化不良を起こしたのでは不健康です。呑み込んでもしっかりと消化できるように胃袋を鍛えておかないとダメです。それでも胃袋には個人差がある、大食いチャンピオンの胃袋の大きさは先天的なものでしょうし、胃酸の量にも個人差があります。無理をしすぎて、イソップ童話の「蛙(かえる)と牛」のような悲劇が起こってはなりません。運ばれてきたご馳走が多すぎる時は、箸をつける前に、誰かに手伝ってもらうとか、箸をつけた後なら、お土産に持ち帰るとか工夫しましょう。呑み込むものが複雑な人間関係の問題だったりする場合は、ずっと厄介ですが、自分一人で抱えるのは少しシンドいなという場合は、他の人に少し頼ってみるほうが現実的な対応と言えますね。信頼できる誰かに悩みを相談してみる、吐き出してみるんです。「呑んで吐き出す」というわけです。そこから何か解決策が見えてきたり、少し気持ちが楽になったという経験は誰でもあると思います。それに、相談している、そのうちに相手の助言が「腑(ふ)に落ちる」ということもあると思います。それこそ、相手の意見や考えを「呑む」ということではないでしょうか。
法話12.涅槃会に因んで「死」を考える
死の恐怖や痛みが問題だという見解があります。“DEATH”(「死」とは何か)の中で、イェール大学の名物教授シェリー・ケーガンは、死の恐怖の分析を進めて、実は死が恐ろしいのは、「死に伴う痛みが恐ろしい」のではないか、「死そのものが恐ろしい」のか(この場合は「死んだらどのようになるか」といった死後の状態を恐れているのではないか)、あるいは「予想外に早く死ぬかもしれないのが恐ろしい」のか、といった仮定を立て論理的に検討しています。
そして、それらは別の感情を引き起こすことがありえたとしても、恐怖の感情を起こす原因とするのは不合理であり、過剰反応であり、錯覚であると結論付けています。これらの説明は確かに死を恐れることの不合理な側面を排除するのに役立つとは思いますが、そうだとしても、死が何らかの不安・恐怖と結びついていることは紛れもない事実です。もともと死の恐怖は不条理なものだと思います。しかし、別の観点で死の恐怖について語っている文を目にしたこともあります。死の恐怖を抱くことは、他の動物と異なる人間の生物学的ハンディキャップなのだというのです。なかなか興味深い見解ですね。
ところで、死を目前にした人間は自分の腑に落ちる考えを求めて色々考えるのだと思います。著名な宗教学者の岸本英夫博士は「生死観四態」と題する文章の中で、多様な生死観を以下のように類型化しています。
一、 肉体的生命の存続を希求するものこれらのうち、いずれの死生観を受け入れるのか、あるいは結局結論を得られずに死を迎えるのかは分かりませんが、人間はみんな自分自身で死と向き合い、その結果として死を受け入れねばなりません。道元禅師の言葉を借りるならば「無常たちまちに到る時は、・・・ただ一人黄泉に赴くのみなり」です。一遍上人も「六道輪廻の間にはともなふ人もなかりけり独りうまれて独り死す生死の道こそかなしけれ」と唄っています。
二、 死後における生命の永存を信ずるもの
三、 自己の生命を、それに代る限りなき生命に托するもの
四、 現実の生活の中に永遠の生命を感得するもの
*『死を見つめる心』より
こうした先人の言葉の中には自分の心にしっくりくるものがあるかもしれません。最近読んだ遠藤周作氏の言葉は、私の心に響くものでした。
次なる世界
人は老いて神に近づくという考え方が東洋にはあったでしょう。能の翁に私は神の姿を感じます。無理して「美しい熟年」なんて言っているけど、熟年にしても、ましてや老年は美しくありません。美しくはないが神々しさというものを感じる、そういう感じ方が私の子供の時にはあったように思います。むかし老人が尊敬されたのは「次なる世界」に近い人だったからです。「次なる世界」を我々が信じなくなってから、老人はもう尊敬の対象ではなく、せいぜい憐憫をかけるべき相手になりました。 …中 略… 若い時は肉体的な感覚で世界を識る、それを肉体の時代と言っておきましょう。中年になると肉体は衰え、心の時代、もしくは知性の時代といったらいいかもしれません。心や知性で世界をつかみます。老年になると、肉体も知性も衰えますが、知性のもっと奥にある魂によって、次なる世界から来る発信音を、肉体の時代よりも、知性の時代よりも聴くことができるのではないでしょうか。
永遠の海 命の海遠藤周作はキリスト者でしたが、その言葉には、私たち日本人の霊魂観・生命観にも繋がる、どこか東洋的な響きがあると思います(感応道交)。静寂の中で滅に入られた(入寂)お釈迦さまの「涅槃会」に因んで、「死の静寂」の内に「宇宙生命の胎動」を聞いた遠藤の言葉を味読してみたいと思いました。
私は老年とは若い時や中年の時とはちがって、何かにじっと耳傾ける時だと思っているのです。その何かとはやがて旅だって行く次なる世界からかすかに聞こえてくる音なのです。 …中 略… キリスト教信者でない方も、その時には自分を超えた大きなものに「すべてを委ねる」という気持ちにはならないでしょうか。自分を今日まで包んでいた大きな生命、自分を越えた大きな生命をそれまでは信じていなくても、病床にあればやはり考えもなさるでしょうし、ひょっとしたら、死を前にした鋭敏な感覚でそれを感得するかもしれません。 …中 略… だから、私たちは必ずしも死の沈黙を絶対に無の沈黙・消滅の沈黙と重ねあわせることはできない気がするのです。茶室に正座している人は、茶室の静寂を内容空虚な静かさとは思いません。その空間のなかには、宇宙の生命にふれる何かが含まれています。禅堂の静かさや無をたんなる虚無と思われる方はいないでしょう。死の直後、あの静かさ、一人の人間が息を引きとった瞬間の静寂。その静寂の向こうに、次の世界が広がっている、これは私自身の感覚ですから、ほかにどう説明のしようもありません。
遠藤周作『死について考える』
法話13.「小林一茶」のこと、したたかな人生について
11月19日は小林一茶の命日だそうです。句集『おらが春』に収載された「露の世は露の世ながらさりながら」は悲しくも秀逸な一句です。一人娘「さと」を病気(疱瘡)で亡くした一茶の深い哀しみと言葉にならぬ慟哭が聞こえてくるようです。無常をいくら理屈で知っていても、どうにもならない悲痛な叫びがそこにはあります。事情を知らなかったときに一茶のこの歌をこう理解していました。「この世ははかない。人々の命も夜露のようにちっぽけで短い。そうだけれども捨てたもんじゃない。その束の間の人生のそれぞれに美があり真実があるのだから」と。
しかし、娘の死というエピソードを知ってからは、この句にさらに深い思い入れを持つようになりました。これは、一茶が受け入れがたい娘の死を受け入れるために、書かねばならなかった句なのだと思います。人間はどんなに哀しく辛いことがあっても、それでも生きてゆかねばならないのです。
こうした人の生きる姿を吉田拓郎はこう詠いました。「わたしは今日まで生きてみました、そして今わたしは思っています、明日からもこうして生きて行くだろうと」(『今日までそして明日から』より)。ここには人間の「したたかさ」が垣間見えるようで、少し頼もしい気がします。
最近、『絵本はこころの処方箋』という本を読みましたが、言葉の少ない絵本を大人が読む場合、行間を経験で補うので、さまざまな解釈が生まれると書かれていました。むしろそれは自然なことですし、そこに読み手の性格や人生観が現れるというのです。ここにも人生の厚みというか、深みというか、味わいというか、そういう何かが作用しているのだと思います。そう考えてみると、「人生捨てたもんじゃない」という人間讃歌のような感覚にとらわれるのです。避け難いことですが、そこにはちょっぴりの悲哀、ペーソスがあります。そういう感覚を背負いながら、私たちの人生は確実に終わりに近づいてゆくのだと思います。この一茶の句が私たちの心に響いてくるのは、私たちが人間の儚(はかな)さと強(したた)かさに共鳴しているからではないでしょうか。
法話14.無用の用について
居間の窓から外を眺めていました。視線の先の瓦屋根の上にテレビアンテナが立っていました。使われなくなったテレビアンテナ、UHFブースター・アンテナ付き。
地上波放送が始まり、ケーブルテレビも普及している現在では、もう何の役にも立たないと思っていたら、そうでもないんです。
アンテナには、キジバトやヒヨドリなど、鳥たちが入れ替わり立ち替わり止まっています。止まって周りの様子を伺うものや羽繕いを楽しむもの、恋を囁くカップルもいる。アンテナは今や鳥たちの休憩場としてちゃんと役に立っているのです。
そこでふと思いました。「役立たずなものなんて何もないのかもしれない」と。「この世の中に無駄なものなどないのだ」「すべてのものがそこに存在することには意味があるのだ」などという言葉はしばしば耳にしてきました。そして、「そんなのは誤魔化し、気休めの言葉に過ぎない」と自嘲したこともありました。でも、今回の「アンテナ観察」経験は、私の見方を少し変えてくれるものでした。たしかにこの経験は「すべてのものは、この世界を構成する唯一無二のワンピースなのだ」という実感を伴っていました。それに、それが役立つものか、まったくの無用の長物なのかを決めるのは、実は私たち人間だけではありませんね。視野を拡げてみると、私にとって無用と思えるものが、他の人には大いに役立つことがあります。また、私たち人間には無用と思えるものが、他の生き物には役立つということもあるんです。
法話15.世俗化について
今はあらゆる領域で「世俗化」が進行している時代だといわれます。この言葉にはさまざまな内容が含まれ、かつては宗教の衰退と科学的世界観の浸透に関連づけられていました。たしかに現在は科学的思考がすべての領域に影響を拡大し、宗教以外の領域にも同様の状況が見られます。
ところで、現代社会には多様な知識があります。そして、その全てが一般の人々に理解できるわけではありません。それで、いわゆる専門的な知識というのは、何らかの解説を施されて私たちに伝えられているのです。世俗化という言葉の意味にこうした事柄も含めるなら、科学的な専門知識自体も世俗化されつつあるといえるでしょう。
このことは一般の人間が科学的発見を自己の認識に取り込み、共有するということでもあり、逆に科学的知識について、見解を述べる権利を獲得したかのように錯覚することでもあります。
宗教についても、そういう意味での世俗化の波は容赦なくおとずれています。科学的知識は、宗教的権威が一般の人たちに提供してきた、一方的な宗教教義とは異なる見解を提示するとともに、人々が宗教に対して意見を述べる上での基礎的な知見と手段を提供することにもなりました。
しかし、この意味での宗教の世俗化によって、人間は聖なる領域を失ってしまうかもしれません。果たしてそれは良いことなのでしょうか?もし、すべての宗教的な価値が権威を失い軽薄なモノと化して、それを共有したからと言って何が面白いのでしょうか。すべての分野・領域に、このような世俗化(簡略化?)」が進行する現在、そろそろ私たちは世俗化の潮流の川底に足がつきそうです。むしろ、果敢に川底を蹴って、神聖な領域の回復、聖化・浄化の方向に勇躍するべきなのではないか。少なくとも、一方的な世俗化の進行がもたらすリスクについて考える必要があると思います。
少し難しい話になりましたが、例えば、私たちは、日常生活の中でいろいろな電化製品を使います。その構造や操作方法は、取扱説明書をまずは読みますね。それで、その機器について知ったように思ってしまうのですが、機器が故障した時、自分で修理できるかと言ったら、多くの場合お手上げ状態になります。その機器について十分に理解しているわけではなかったと思い知らされるわけです。一般人の科学技術知識は利便性や危機管理のための最低限のものなんですね。「それでとりあえず良いんじゃないか」という意見もありますが、それが完全な知識ではないということを、心の片隅に置いておくことが大事だと感じます。
法話16.月と禅
猛暑の夏でした。近年猛暑でない歳は聞いたことがない。少しでも涼を求める無意識が働いたのか、新しく「風鈴(ふうりん)」を買いました。
その美しい鈴の音に癒された季節も終わり、今は「鈴虫」の季節です。ところで、鈴虫の異称に「月鈴子(げつれいし)」というのがあります。月の世界から舞い降りた小さな鈴という意味だそうです。そして、その鈴虫の故郷である「月」というのもポピュラーな季語です。月は春夏秋冬いつでも季節の季語になります。冬の寒月、春の朧月(おぼろづき)など、年間を通して愛(め)でられる月ですが、何といっても名月といえば「仲秋の月」です。「芋(いも)名月」とも言われて月見団子や里芋などを供えます。元は芋などの収穫を祝う儀式であったともいわれるようです。
この月と禅の関わりも深く、わが道元禅師も「春は花、夏ほととぎす、秋は月・・・」と殊のほか月を愛でていらっしゃいます。宝慶寺に伝わる「観月図」「月見の像」は、この仲秋の名月を眺めておられる姿でしょうか。ついでと言っては何ですが、「鳴く」という言葉も俳句の季語になります。不思議なものが鳴きます。春は「亀」や「田螺(たにし)」が鳴き、秋には「蚯蚓(みみず)」や「蓑虫(みのむし)」が鳴くそうです。どんな鳴き声でしょうか?「カメやタニシは「キュウ」ですか?聞いたような、聞かなかったような・・・。ミミズやミノムシの鳴き声は聞いた覚えがありません。こうして、秋の夜長のしじまの中で、どこまでも続く連想の糸を辿りながら夜坐を愉しむというのも風流ではありませんか。
法話17.坐禅という行為−成道会に因んで
禅宗は坐禅を強調しますが、それは坐禅を仏教の最も基本的根源的な行為と見て、宗派の特徴としているということでしょうね。お釈迦様は坐禅をして成道したと言われていますから、坐禅はお釈迦様の修行の追体験としての行為ということになり、しかもそれは、釈尊が悟りに到達した時に用いた行為ということになります。
それでは坐禅を特徴づけているのはどういうことかと考えると、例えば六波羅蜜の中で坐禅以外の項目はみな極めて人間的かつ日常的な行為なのです。しかもいたって能動的な行為です。というのも、戒律を守ったり、智恵を磨くのはもとより、忍耐というのも動物は不得手な行為であるし、努力も動物にはできないからです。ところが、坐禅の求めるところが「あるがままの現状を受け入れる境地」だというのなら、それはむしろ動物と同質の受動的境地なのではないか、猿学の先生によるとゴリラなどの類人猿が病気になったときには彼らは病気の自分を受け入れるのであって、それを治そうとはしないそうですから、坐禅の究極的境地は動物心と類似しているのであって、言い換えれば、坐禅は人間が自身の動物的身体的本源へ回帰する道なのではないかというわけです。ハイデガー的にいうなら、現存在の「被投的」側面とでも言われる事態の体認といったところです。
こう考えると、坐禅は、少し非日常的で受動的な行為です。そうだとすると、六波羅蜜の中では坐禅と他の五項目は真逆のベクトルを示すと考えられるのではないでしょうか。この際、人間の動物性と人間的特性の相違相関を考えてみるのも面白いと思いました。